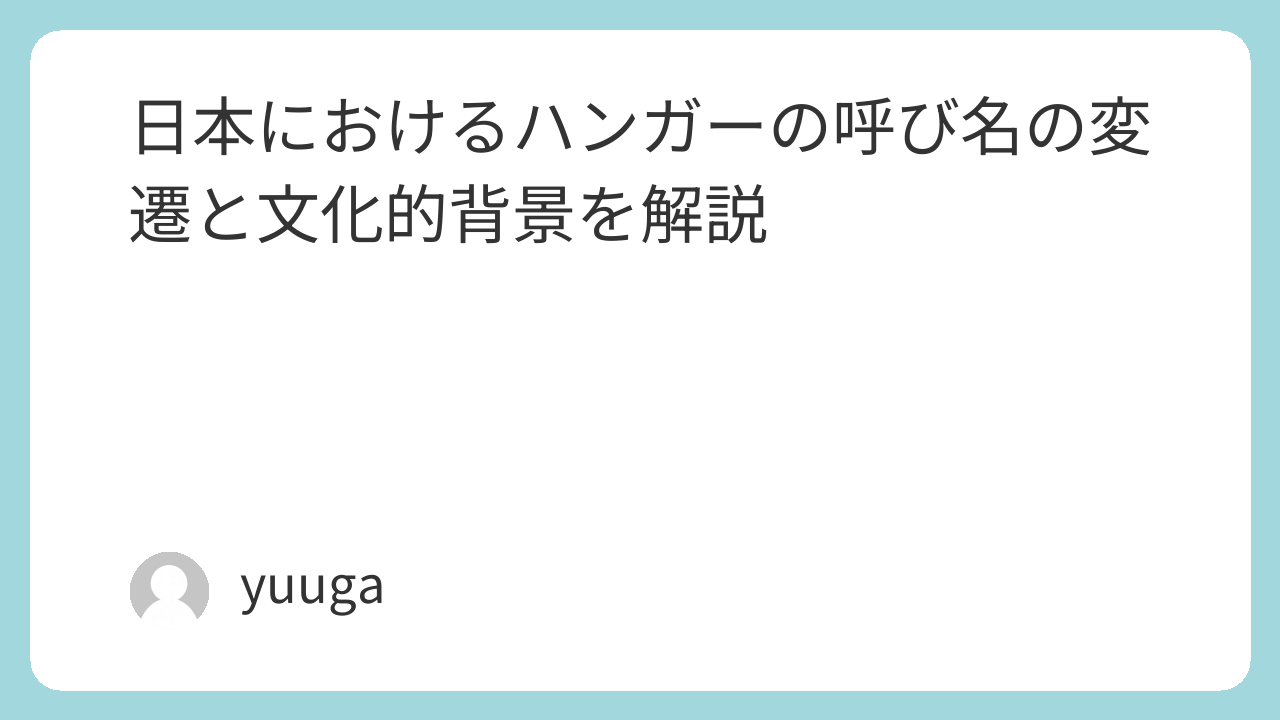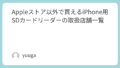日本におけるハンガーの歴史と呼び方の変遷
衣紋掛けとは何か?
「衣紋掛け(えもんかけ)」は、着物や衣類をかけて形を整える道具のことで、かつての日本では一般的に使われていた呼び名です。特に和服においては、着物の肩のラインを崩さずに保管するために重宝されてきました。
また、衣紋掛けは季節ごとの衣替えや着物の陰干しにも使われるなど、家庭での衣類管理には欠かせない存在でした。木や竹など、通気性のよい自然素材で作られることが多く、日本の風土にも適していました。
ハンガーに変わった理由
明治時代以降、西洋文化の影響で洋服が普及するとともに、「ハンガー」という呼び名も一緒に輸入されました。ハンガーは英語の”hanger”に由来し、洋服の形状や素材に合った形をしていることから、実用性とともにその名称も徐々に広まりました。
特に大正から昭和初期にかけては、洋装が広がる中で「衣紋掛け」と「ハンガー」が併用される時期もありました。現在では、和装の機会が限られてきたことから、「衣紋掛け」という語はあまり使われなくなっています。
昔の言い方の一覧
- 衣紋掛け(えもんかけ)
- 掛け物(かけもの)
- 衣類掛け
- 着物掛け
- 掛け竿(かけざお)
- 押し入れ掛け
- 湿し掛け(しめしかけ)
これらの呼び方は、主に和服を対象としており、素材も木製や竹製が主流でした。地域によっては独自の呼称が残っている場合もあります。
言葉の減少と文化的影響
「衣紋掛け」という言葉が日常で使われる機会は、洋服中心の生活に変化する中で少なくなりました。呼び方の変化は、生活様式や衣類のスタイルだけでなく、日本語そのものの変化と密接に関係しています。
現代では、家庭用品店でも「衣紋掛け」の名で販売されることはまれであり、文化的記憶の中でのみ残されつつあります。とはいえ、伝統芸能や祭礼の場では、衣紋掛けという語や道具が現役で活躍している例もあります。
ハンガーと衣紋掛けの違い
衣紋とハンガーの役割
衣紋掛けは、主に着物や和装を整える目的で使われるのに対し、ハンガーは洋服を吊るす道具としてより汎用的な用途があります。
和服と洋服における使い分け
和服は素材が柔らかくシワがつきやすいため、肩のラインを保持するために横に長く、先端が丸くなった衣紋掛けが使われます。洋服は衣紋掛けよりも立体的な形状のハンガーが適しています。
ハンガーの種類と形状
和装用ハンガーの特徴
和装用のハンガーは、着物が風通しよく乾くように長くて平たい形をしています。中には伸縮可能なものもあり、着物の袖をしっかり広げて掛けることができます。
収納方法の変化
クローゼットや洋服ダンスの普及により、衣類を「畳む」文化から「吊るす」文化へと変化しました。これにより、より多機能でコンパクトなハンガーの需要が増えました。
衣類の収納と管理
着物とハンガーの関係
着物は本来、畳んで収納するものとされてきましたが、一時的に掛けておくための衣紋掛けは、着付け前後の整頓に欠かせない存在でした。
洋服の収納法の進化
現代ではシワを防ぎ、見た目を整えるために、多くの洋服がハンガーに吊るされて保管されます。また、ハンガーには滑り止めや型崩れ防止機能付きのものも多く登場しています。
素材もプラスチックや木製、金属製など多様で、衣類の種類や使用シーンに応じて選ばれるようになっています。さらに、省スペース型や折りたたみ式、360度回転するフック付きなど、現代の生活スタイルに合わせた製品も豊富に揃ってきました。
特にファッションへの関心が高まる現代では、衣類をきれいに保管するだけでなく、見せる収納としての機能も重視され、ハンガーのデザイン性も向上しています。
死語としての「衣紋」
現代の言葉としての意義
「衣紋」は今ではあまり使われなくなった言葉ですが、茶道や能、着付けの世界ではいまだに大切に使われています。これらの伝統文化においては、衣紋という言葉が持つ意味は単なる衣類のことだけにとどまらず、身だしなみや礼儀作法の一部として重視されます。
また、伝統芸能の継承においては、古語や古い言い回しも重要な要素とされており、文化を構成する語彙として「衣紋」は今なお息づいています。現代でも着物教室や茶道教室などの一部では、新しい世代にその意味を伝える取り組みがなされています。
言葉の変化が示す文化的背景
言葉の移り変わりは、文化の変化を映す鏡とも言えます。衣紋掛けという言葉の衰退は、和装文化の縮小や生活スタイルの欧米化と深く関係しています。
衣紋という言葉が使われなくなる背景には、和装の特別性や日常からの距離が大きく影響しており、日本の住環境やライフスタイルが大きく変わったことも一因です。一方で、復古的な価値観や和文化の再評価が進む中で、こうした言葉が再び見直される機運もあります。
言葉の保存は、文化そのものの保存とも言えるため、衣紋という言葉が持つ意味を知り、使うことは、現代の私たちにとっても重要な行為なのかもしれ
まとめ
ハンガーという呼び方は、洋服の普及とともに一般化しましたが、「衣紋掛け」には日本独自の生活様式や美意識が反映されています。呼び名の変化をたどることで、衣類文化の変遷だけでなく、日本語や暮らしの変化をも感じ取ることができます。